はじめに:検索体験の大きな転換期
2020年代に入り、ChatGPTをはじめとする「生成AI(Generative AI)」が急速に進化し、私たちの情報検索の方法に革命的な変化をもたらしつつあります。これまで検索エンジンの代名詞であったGoogleも、検索結果にAIによる要約を表示する「SGE(Search Generative Experience)」を導入するなど、その動きは加速しています。
ユーザーはもはや、青いリンクの一覧から答えを探すだけでなく、検索エンジンが直接生成する「回答」によって、より迅速に情報を得られるようになりました。この変化は、ウェブサイトへの集客を目的とするSEO(Search Engine Optimization)に、新たな対応を迫るものです。
本シリーズ「生成AI時代のSEO学習シリーズ」では、この大きな転換期においてWebマーケターやサイト運用者が知るべき知識を、基礎・応用・実践の3つのステップで体系的に解説します。本記事では、シリーズの導入として「生成AI時代のSEO」が何を指すのか、従来の手法と何が違うのか、そして私たちはどのような新しい課題に直面しているのかを整理します。
1. 従来のSEOとその基本原則
生成AI時代のSEOを理解するためには、まず従来のSEOが何を目指していたのかを再確認する必要があります。
従来のSEOの主な目的は、特定のキーワードで検索された際に、自社のウェブページを検索結果の上位に表示させることでした。そのための基本的なプロセスは以下の通りです。
- キーワードリサーチ:ユーザーがどのような言葉で検索するかを調査・分析し、ターゲットとするキーワードを選定する。
- コンテンツ制作:選定したキーワードを適切に含み、かつユーザーの検索意図を満たす高品質なコンテンツを作成する。
- 内部対策:サイトの構造を検索エンジンが理解しやすいように最適化する(タイトルタグの設定、内部リンクの整備など)。
- 外部対策:他の質の高いサイトからリンク(被リンク)を獲得し、サイトの権威性や信頼性を高める。
この根底には、Googleが掲げる「ユーザーに最も価値ある情報を提供する」という理念があります。検索エンジンは、ユーザーの質問に対して最も的確で信頼できる答えを持つページを高く評価しようとします。この「ユーザーファースト」という基本原則は、生成AI時代においても変わることはありません。むしろ、その重要性はさらに増していると言えるでしょう。
2. 生成AIがSEOにもたらした3つの大きな変化
生成AIの登場は、従来のSEOの常識を覆す可能性のある、いくつかの大きな変化をもたらしました。
変化1:検索エンジンから「回答エンジン」へ
最も大きな変化は、検索エンジンが単なる「ウェブページの案内役」から、自ら「回答を生成する存在」へと変わりつつあることです。
- Google SGE (Search Generative Experience):Google検索の結果ページ最上部に、AIが生成した要約や回答が表示される機能です。ユーザーはリンクをクリックせずとも、この要約だけで疑問を解決できる場合があります。
- Bing Chat:Microsoftの検索エンジンBingに搭載されたチャット機能。ユーザーと対話しながら、Webの情報を基に回答を生成します。
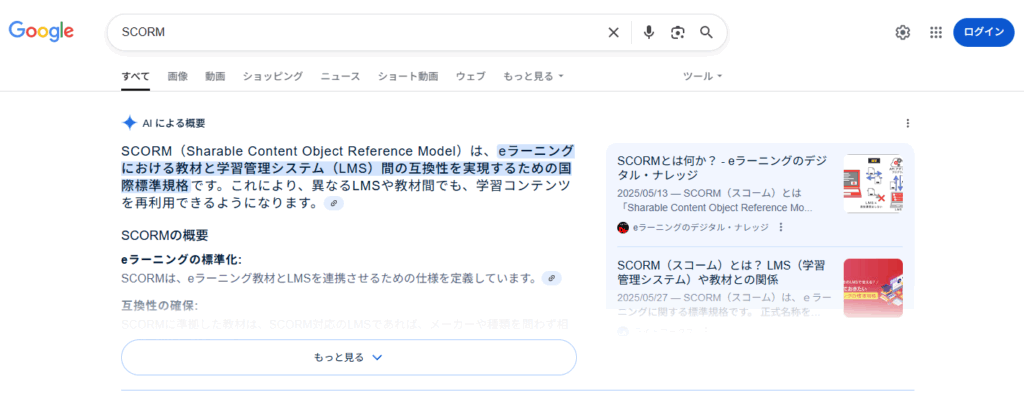
これにより、ウェブサイト運営者が懸念すべきは「ゼロクリックサーチ(Zero-Click Search)」の増加です。ユーザーが検索結果ページのAI回答に満足し、ウェブサイトを訪問(クリック)せずに検索を終えてしまう現象を指します。これは、サイトへのトラフィック(流入数)の減少に直結する可能性があります。
変化2:新たな情報検索チャネルの台頭
これまでは「検索といえばGoogle」が当たり前でしたが、生成AIの登場により、情報収集の選択肢が多様化しました。
- 大規模言語モデル(LLM)チャットサービス:ChatGPTやClaudeなどは、対話形式で様々な質問に答えてくれます。レポート作成やアイデア出しだけでなく、何かを調べるためのツールとしても利用され始めています。
- AI検索エンジン:PerplexityやYou.comといった新興サービスは、従来の検索エンジンとAIチャットを融合させたような体験を提供し、注目を集めています。
これらのサービスは、必ずしもGoogleのようにリアルタイムでWeb全体をクロールしているわけではなく、巨大な学習データに基づいて回答を生成します。つまり、Googleの検索順位で1位を取るだけでは、これらのAIに情報を参照してもらえない可能性があるのです。
変化3:求められるコンテンツ品質の再定義
AIがユーザーの代わりに情報を読み込み、要約して提示するようになったことで、コンテンツに求められる質も変化しています。
AIに要約されてもなお「この記事を直接読みたい」と思わせる付加価値や、AIが「信頼できる情報源」として引用したくなるような権威性が不可欠になります。ここで改めて重要になるのが、Googleが品質評価ガイドラインで示す「E-E-A-T」です。
- Experience(経験):著者がそのテーマについて実体験を持っているか。
- Expertise(専門性):著者がそのテーマの専門家であるか。
- Authoritativeness(権威性):著者やサイトがその分野の権威として認められているか。
- Trustworthiness(信頼性):情報が正確で信頼できるか。
表面的な情報をまとめただけの記事はAIに代替されやすく、これからは独自のデータ、深い洞察、具体的な経験談といった、AIには生成できない一次情報がコンテンツの価値を左右します。
3. 生成AI時代における新たなSEO概念
これらの変化に対応するため、SEOの世界では新しい最適化の考え方が生まれています。本シリーズでは、これらの概念についても詳しく掘り下げていきます。
- AEO (Answer Engine Optimization)
- 「回答エンジン最適化」と訳されます。SGEや強調スニペットなど、検索結果に直接表示される「回答」部分に自社コンテンツが採用されることを目指す施策です。FAQページの作成や構造化データの実装などが含まれます。
- GEO (Generative Engine Optimization)
- 「生成エンジン最適化」と訳されます。Google SGEやBing Chatといった生成AIが回答を作る際に、自社のコンテンツを情報源として引用・参照してもらうことを目指す施策です。
- LLMO (Large Language Model Optimization)
- 「大規模言語モデル最適化」と訳されます。ChatGPTなどのLLMが学習するデータセットに、自社のブランドや情報が含まれ、記憶されることを目指す長期的な戦略です。専門性の高い情報を発信し続けることで、その分野の第一人者としてAIに認識させることが狙いです。
これらの用語はまだ新しいものですが、いずれも「ユーザーとAIの両方から信頼され、選ばれるコンテンツをいかに作るか」という点で共通しており、従来のSEOの延長線上にある考え方と捉えることができます。
4. 事例:海外メディアの動向
生成AIによる影響は、すでに実際のデータとしても観測され始めています。SEO分析ツールを提供するAhrefs社は、自社ブログでSGEが検索トラフィックに与える影響について分析しています。
同社の調査によると、SGEが表示されることで、従来のオーガニック検索結果へのクリックが奪われる可能性があると指摘されています。特に、簡単な答えを求めるような情報収集クエリ(Informational Query)ではその傾向が強いと予測されています。
参考URL: Google AI Overviews: All You Need to Know – Ahrefs Blog
このような分析は、ウェブサイト運営者が今後、どのようなキーワードを狙い、どのようなコンテンツを作成していくべきかを考える上で重要な示唆を与えてくれます。
5. まとめ:今後の課題と本シリーズで学ぶこと
本記事では、生成AIの登場がSEOの世界にどのような変化をもたらしているのか、その概要を解説しました。私たちが直面している課題は、以下のように整理できます。
- トラフィック減少への対策:ゼロクリックサーチが増加する中で、いかにしてサイトへの訪問を促すか。
- 新たな検索体験への最適化:SGEやAIチャットでの露出をいかにして増やすか(GEO/AEO)。
- AIに引用されるコンテンツ戦略:E-E-A-Tを意識し、AIから信頼される情報源となるにはどうすればよいか。
- ブランド認知と信頼性の構築:検索順位だけでなく、LLMに記憶されるようなブランド価値をいかにして築くか(LLMO)。
これらの課題は、決して簡単なものではありません。しかし、変化の本質を理解し、適切に対応することで、新たな機会を掴むことも可能です。
本シリーズでは、次回以降、今回登場した新しい概念や具体的な施策について、一つひとつ丁寧に解説していきます。次の「基礎知識編2」では、「検索エンジンから回答エンジンへ」というテーマをさらに深掘りし、ユーザー行動の変化とSEOの概念がどのように変わってきたのかを詳しく見ていきます。
生成AI時代のSEOという新しい航海に、ぜひ本シリーズをお役立てください。